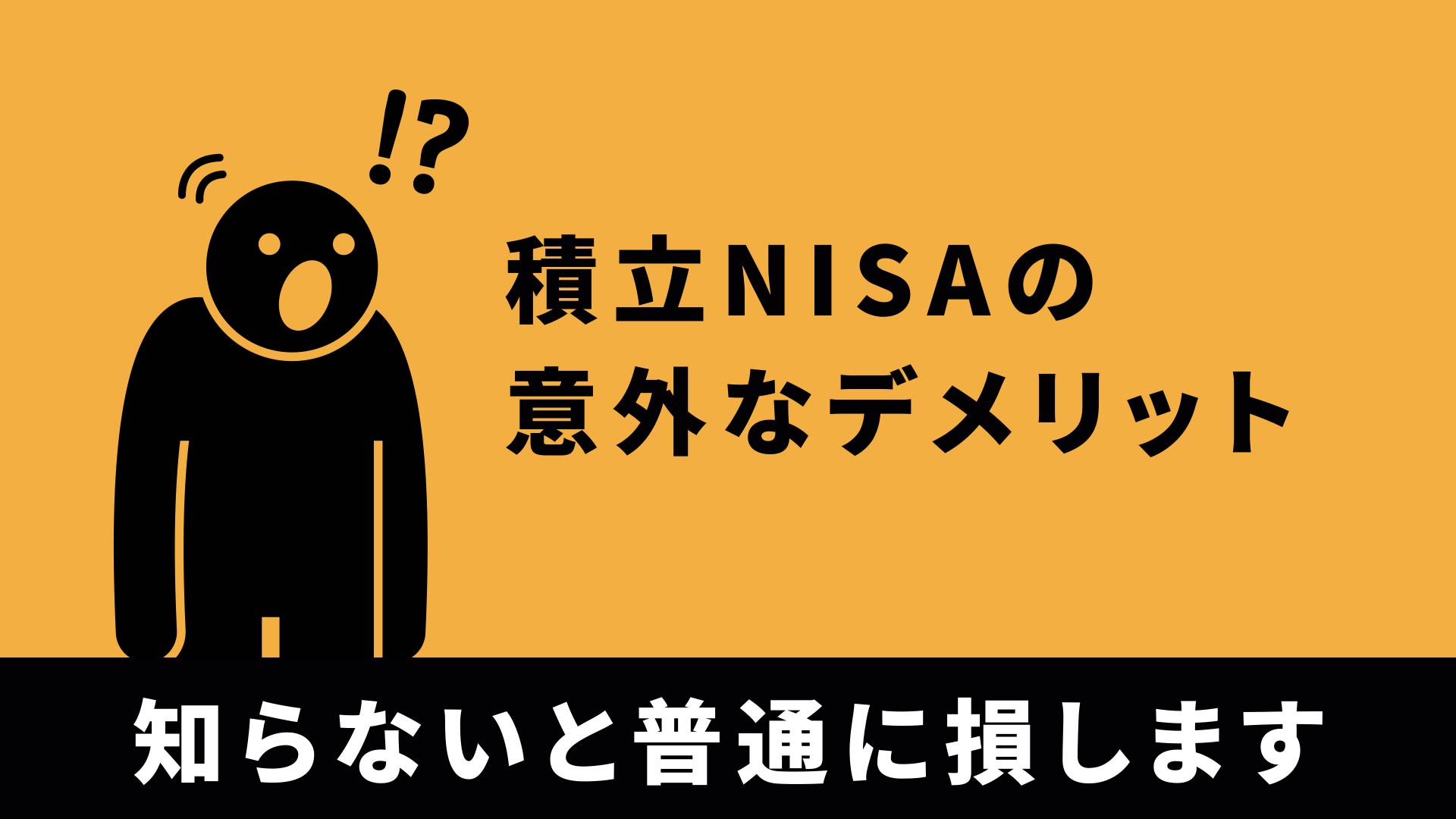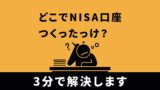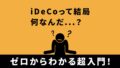積立NISAって本当にお得なことばかりなの?
「積立NISAって、とにかくお得な制度なんでしょ?」
そんなイメージを持っていませんか?
たしかに、積立NISAは運用益が非課税になったり、少額から始められたりと、初心者にとって心強い制度で筆者も日頃からおすすめしている制度です。
ですが、実は「注意しないと損する落とし穴」もあるんです。
この記事では、積立NISAの“意外なデメリットとその対策を、投資初心者の方にもわかりやすく解説します。
「始めたけど思ってたのと違った…」「知らずに損をしていた…」と後悔しないために、ぜひチェックしてみてください!
新NISAのつみたて投資枠(積立NISA)とは?おさらいしておこう
新NISAのつみたて投資枠(積立NISA)は、少額からコツコツ投資をはじめられる“国のお墨付き”の制度です。投資信託などで得た利益にかかる税金(約20%)が非課税になるので、利益が出た分はまるっと自分のものになります。
「え、税金かからないの?夢じゃない?」と思ったそこのあなた、そうです。
夢のような制度…に見えますが、実は注意点もあるのです。
つみたて投資枠は”投資初心者の入門編”として非常に優れた制度である一方、正しく理解して使わないと「思ってたのと違う…」と後悔することもあるのです。
↓つみたて投資枠について、詳しくは下記の記事でも説明していますので参考にしてみてください
つみたて投資枠(積立NISA)の意外なデメリット
それでは早速本題のNISAのつみたて投資枠の意外なデメリットについてみていきましょう。
先に結論は下記です!
・年間投資上限がある
・短期間では大きく増えない可能性がある
・途中で銘柄を変更しすぎると効果が薄れる
・対象商品の種類が限られている
・「利益に税金がかからない」だけではない
年間投資上限がある
積立NISAでは、年間120万円までしか投資できません。
「お金に余裕あるし、もっとガッツリ投資したいんだけど!」という人にとっては、ちょっと物足りないかもしれません。
もっと投資したい人は、同じNISA制度内の「成長投資枠(旧・一般NISA)」や特定口座を併用するのがオススメです。短期で結果を出したいなら成長投資枠や特定口座と併用しましょう。
短期間では大きく増えない可能性がある
NISAのつみたて投資枠は“長期投資”が前提です。10〜20年というスパンでコツコツ積み上げるので、短期間でドカンと増えることはまずありません。
「3年くらいで2倍くらいになるって聞いたんだけど…?」という期待は禁物です。これは“スロースターター型”の投資なんです。
焦らず、地道に。短期で結果を出したいなら成長投資枠や特定口座と併用しましょう。
途中で銘柄を変更しすぎると効果が薄れる
積立NISAのキモは「ドルコスト平均法」。 毎月同じ額を同じ商品に投資することで、高値づかみを避けつつリスクを抑えられます。
でも、ちょっと成績が悪いからといってすぐに別の銘柄に変えてしまうと、せっかくのドルコスト効果が台無しに。
最初に選ぶ銘柄は慎重に。でも一度決めたら、よほどの理由がない限り“浮気しない”ことがコツです。
対象商品の種類が限られている
積立NISAで買えるのは、金融庁が厳選した“優良投資信託”のみ。つまり、商品数がかなり絞られているんです。
「もっと色々選びたい!」「個別株にも投資したい!」という方には物足りないと感じるかも。
逆に考えれば、変な商品に手を出さずに済む“初心者向けフィルター”とも言えます。自由度が欲しい人は、成長投資枠の活用も検討しましょう。
「利益に税金がかからない」だけではない
よくある誤解に、「積立NISAなら配当金も全部非課税でしょ?」というものがあります。
実は、つみたて投資枠の「NISA口座」で運用していても、分配金が自動的に再投資されるタイプの商品でなければ、税金がかかる場合もあるのです。
「分配金再投資型」を選ぶことで、非課税メリットを最大限に活かせます。
よくある失敗パターンと対策法
それではここからはよくある失敗パターンと対策について解説しますので参考にしてみてください。
まとめると下記です。
・投資額の設定が高すぎて生活を圧迫
・商品をあまり調べずに選んでしまう
・値下がり時に不安になって解約してしまう
・複数口座の開設ミスや移管の手間
投資額の設定が高すぎて生活を圧迫
「よし!将来のために月3万円積み立てるぞ!」と意気込んだのはいいけれど、翌月には「やっぱりキツい…ランチ代すらケチらないと…」なんてことに。
積立NISAは“長く続けること”が重要なので、最初から無理な金額設定をすると継続が難しくなります。
月5,000円から始められるので、まずは“コンビニのコーヒー代レベル”でスタート。慣れてから増額すればOKです。
商品をあまり調べずに選んでしまう
「人気って書いてあるし、とりあえずこれでいっか!」と選んだ投資信託。あとで調べたら、手数料が高かったり、値動きが激しすぎたり。
ネットで「初心者におすすめ」とされている商品でも、自分に合っているとは限りません。
銘柄選びのポイントは「信託報酬が低い」「資産が分散されている」「純資産がしっかりある」の3つです。
値下がり時に不安になって解約してしまう
投資信託の価格が下がると、「うわっ!マイナスじゃん!やめようかな…」と焦って解約。結果、安値で売ってしまって損を確定…という悲しい展開に。
これは、投資あるあるの“狼狽売り”と呼ばれるものです。
積立NISAは10年〜20年の長期目線が前提です。
短期の値動きに惑わされず、「今はセール期間」と考えるぐらいの気持ちで継続しましょう。
複数口座の開設ミスや移管の手間
「あれ?楽天でNISA口座作ったっけ?それともSBIだっけ…?」と記憶があいまいなまま、うっかり別の金融機関で再度申請→エラー!はあるある。。。
NISAは“1人1口座”がルールなので、複数作ることはできません。
まずは自分のNISA口座がどこにあるか確認(税務署での確認や金融機関への問い合わせ)。すでに開設している場合は、必要に応じて「金融機関変更」の手続きを行いましょう。
↓詳しくは下記の記事で説明しているので参考にしてみてください。
まとめ
積立NISAは、国が用意した“税金ゼロ”のありがたい制度。投資初心者でも少額から始められて、長期で資産形成ができるという意味では、これ以上にやさしい仕組みはなかなかありません。でも、どんなに便利な制度でも、使い方を間違えれば損をすることも。
・無理な金額でスタートして途中でギブアップ…
・よく調べずに選んだ商品がイマイチで後悔…
・値下がりにビビって損切り…
・口座開設ミスでスタートすらできない…
こうした“積立NISAミスあるある”を回避するためには、事前に制度の特徴と注意点を知っておくことが何より大事です。
この記事では、意外と知られていない積立NISAのデメリットや失敗例、その対策まで詳しくご紹介しました。
大事なのは、「焦らず・無理せず・継続すること」。未来の自分のために、毎月の小さな積み立てが大きな安心につながります。積立NISAは、あなたの資産づくりの“相棒”になってくれるはず。
さあ、今日からゆるマネくんと一緒に勉強しましょう!